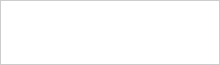聖書箇所:へブル12:1~4
12:1 こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競走を、忍耐をもって走り続けようではありませんか。
12:2 信仰の創始者であり完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。
12:3 あなたがたは、罪人たちの、ご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。
12:4 あなたがたは、罪と戦って、まだ血を流すまで抵抗したことがありません。徳川家康の遺訓は「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。」から始まる。織田家、豊臣家が相手だけではなく、天下統一は振り返って長い道であっただろう。この聖書箇所は、私たちの人生の行く道、走るべき道が示されている。
へブル人への手紙が開かれたが、へブル人とはどこの国の人なのかと思われただろうか。へブル人、イスラエル人、ユダヤ人は、呼び名が生まれた事情は違うが、同じ民族、同じ国民を指している。へブル人と言った場合はヘブル語(ヘブライ語、今もイスラエルの公用語)を話す人々という意味合いもある。
Ⅰ.イエス様は全ての人の救い
この手紙はヘブル語を話すイスラエルの人々に、イエス様による救いを語っている。イスラエルの人々はイエス様以前に、旧約聖書に出てくる長い歴史を通ってきた。
皆様の暮らす街、皆様の家には、どんな宗教的行事があるだろうか。春や秋、それぞれの季節にいわれがある祭りがある。イスラエルの人々が守ってきた旧約聖書の祭りごとと言えるものは、もっとたくさんあった。季節毎ではなく、毎日の日常の中にあった。神様の定められた決まりであるが、これらを守ることが、イスラエルの人々の救いにつながることであった。
旧約聖書が閉じられて、新約聖書が始まるのはイエス様の誕生、クリスマスのできごとからになる。旧約聖書の中で生きてきた、毎日の決まりの中に縛られていたイスラエルの人々に、イエス様こそが救い主であるということを示したのがこの手紙になる。私たちも何かに縛られることはあるが、救いは目の前にある。
Ⅱ.イエス様が始まりで終わりとなる
イエス様は「信仰の創始者であり完成者である」(2節)と記される。イスラエルの人々は自分たちの信仰の父はアブラハムと言う。もしそうであれば、アブラハムを父に持っていない私たちに救いはない。神様が地上に来られたイエス様が、信仰の始まりであれば、私たちは誰でもイエス様によって信仰に入れられることができる。
イエス様は信仰の完成者であるとも言う。イエス様は信仰の到達点、ゴールとなってくださる。信仰を持っても、どこを目指せばよいのか分からなければ手探りであり、とても厳しいだろう。私たちには目指すべき到達点が明らかなのは幸いなことである。だからこそ「イエスから、目を離さないでいなさい。」(2節)と言われる。イエス様を見つめていれば、私たちは人生において迷う必要はない。
Ⅲ.イエス様が助けてくださる
私たちが神様の愛と恵みの内を歩んでいくために、イエス様は侮辱やあざけり、辱めをいとわないで、ご自分が殺されるという十字架を忍ばれて、神様の救いを完成してくださった。それは、私たちが「一切の重荷とまとわりつく罪を捨て」(1節)るためだった。私たちの心を重くさせる、否定的な生き方から解き放ってくださる。
聖書には、どんな人の中にも人生の重荷と、その人をおとしめ卑しめる罪があると語る。私たちは自分の重荷も、罪も、自分の力だけで消すことも、動かすこともできない。イエス様は私たちのどんな重荷も、罪も取り去ってくださる。
例)17世紀のクリスチャン作家、ジョン・バニヤンの「天路歴程」がある。主人公のクリスチャンが滅びの都から天の都に至るまでの人生の道行きの小説である。プロテスタントの宣教団体が新しい国の宣教を始めるとまずその国の言葉で聖書翻訳を始める。次に天路歴程の翻訳を始めたと言われる。自分自身の救いの証し、重荷と罪が取り去られる経験は、私自身を今日まで支えている。
私たちを重荷と罪から解き放ってくださったイエス様のことを考えるならば、心が元気になり、健やかに過ごすことができる。